住宅ローンの借入可能額とは何か
住宅ローンの借入可能額とは、金融機関があなたに貸しても問題ないと判断する上限の金額のことです。年収、勤続年数、借入状況、信用情報などさまざまな要素をもとに決まります。
しかし、単に「借りられる金額」が分かったからといって、それをそのまま使ってしまうのは非常に危険です。本当に大切なのは“いくらまでなら無理なく返済できるか”という視点です。
借入可能額の計算に使われる「返済負担率」とは
借入可能額を決める指標のひとつに「返済負担率」があります。これは、年収に対して年間返済額が占める割合を示したもので、多くの金融機関では30〜35%が基準とされています。
たとえば、年収500万円で返済負担率が30%なら、年間返済額の上限は150万円。これをもとに借入額が逆算されます。
例えるなら、年収を家計というバケツにたとえたとき、「住宅ローンに使ってよい水の量」を測るようなものです。これが多すぎると、ほかの生活費にしわ寄せが出てしまいます。
年収別の住宅ローン借入可能額の目安
実際の目安は以下の通りです。これは金融機関の返済負担率(35%)を想定しておおよその金額を試算したものです。※金利1.5%、35年返済と仮定。
年収400万円 → 約2,800万円〜3,000万円
年収500万円 → 約3,500万円〜3,800万円
年収600万円 → 約4,300万円〜4,500万円
年収700万円 → 約5,000万円〜5,300万円
年収800万円 → 約5,700万円〜6,000万円
**注意すべきは、借入可能額はあくまで「最大値」であること。**生活スタイルや家族構成によって、現実的な返済可能額は大きく変わってきます。
「その金額で本当に審査に通るの?」
【2025年最新版】住宅ローンの審査に通るための条件と落ちる人の共通点を徹底解説
借入可能額の目安が分かっても、実際に審査が通るか気になりますよね。こちらの記事で審査の通過ポイントを詳しく解説しています。
返済可能額と借入可能額の違いに注意
借入可能額と返済可能額は、似ているようでまったく違います。
借入可能額 → 銀行が「これなら貸せる」と判断する金額
返済可能額 → 自分の生活に無理なく返済できる現実的な金額
たとえば、子どもが小さいうちは支出が少なくても、教育費や家族構成が変わると支出は増えます。
未来の家計変化を見据えずに「借りられる額」いっぱいまで借りてしまうと、将来的に家計が圧迫されるリスクがあります。
無理のない返済計画を立てるための考え方
返済可能額から逆算して物件価格を決めることが理想的です。
具体的には:
家計簿をつけて現在の支出を正確に把握する
教育費や車購入費など将来の支出も見込む
「毎月この額なら返していける」と思える返済額を決める
それに基づいて借入額を決定
さらに、ボーナス返済に依存しないことや、繰上げ返済の可能性も視野に入れると、より柔軟で安心感のある計画になります。
「より詳しく知りたい」
【後悔しない】住宅ローンシミュレーション活用法と家づくり成功のポイントまとめ
返済計画を立てるには、実際のシミュレーションがとても役立ちます。こちらの記事でツールの使い方もチェックしてみてください。
実際に借りた体験談から見えた注意点
私自身が住宅ローンを検討した際、銀行から提示された借入可能額は当初想定していたよりも大きく、嬉しさと同時に不安も感じました。
その後、家計を見直してみると、保育料、車検、将来の教育費など、今はまだ見えていない出費が想像以上に多いことに気づきました。
結果的に、借入額は当初の想定より少なめに設定しましたが、毎月の支払いに余裕があることで精神的な安心感が大きいと感じています。
また、住宅ローンの審査にあたって、繰上げ返済が可能な商品や、団体信用生命保険の内容も比較しておくことが非常に重要だと実感しました。
まとめ 将来を見据えた資金計画が大切
住宅ローンの借入可能額は、あくまで金融機関の目安であり、自分の家計や将来設計に合わせた判断が何より重要です。
借入可能額に惑わされず、返済可能額から逆算する
年収だけでなく、支出全体を見直して現実的な金額を設定する
金利・返済年数・団信など、総合的に商品を比較検討する
**住宅ローンは「家を買う」だけでなく「家計を守る」ための選択でもあります。**しっかりと準備をして、納得のいく家づくりを進めていきましょう。

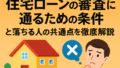

コメント